仕事で自分なりに頑張っている・努力されているつもりだが、なかなか評価されないなと感じる事はないでしょうか?努力することはもちろん大事ですが、苦手な事も自分でやらないと!と思いつつもやはり苦手な事は自分自身がすり減ってしまいます。それで休日は疲れて動けなくなってしまう・・・なんてこともあるのではないでしょうか。
本書では、そのような擦り減らない方法で評価されるかもしれない、そんな方法を提案しています。
本のかんたんな紹介
作者名:けーりん(唐仁原けいこ)
発売年:2024年
出版社:すばる舎
作者の経歴:けーりん(唐仁原けいこ)氏はビジネスパーソンとして、戦略的に周囲と良好な関係を築きながら成功する方法を提唱しており、本書はそのノウハウを体系的にまとめた一冊となっています
対象読者
- 仕事を自分なりに頑張っているが、評価されていると感じていない人
- もっとよりよい仕事の進め方がないか摸索している人
本書は仕事の場面をターゲットにしています。仕事もサラリーマンのように組織の中にいる人から個人事業主など独立した方でも参考になります。また、サラリーマンだと一般社員から管理職まで問わず、個人事業主などで自身がトップの人でも学べる事が多く、対象読者になります。
本書で得られること
「戦略的いい人」とは何か?それがなぜメリットがあるのか、を知ることが出来ます。ただ、これだけだとイマイチピンとこないと思います。私は最初、「いい人」とあったので、なんだかYesマンのようだと感じましたが、実際は全然そんなことはありませんでした。
本書でも戦略的いい人の定義はしていますが、自分が一番率直に思った戦略的いい人をまとめると、「自分が得意な事を周囲にギブして、苦手な事は他人にお願いする。苦手な事を対応してくれたら感謝の気持ちをもって周囲に知らせるなどして、人と人を繋げる人。人以外も繋げる」です。つまりYesマンではありません。何なら、結構良さそうな立ち位置の人だと思いませんか?そんな立ち位置になるにはどうすればよいか、それについての考え方を得る事が出来る書籍です。
本書を読んでみて
本書は全5章で構成されており、各章の概要は以下の通りです:
- 第1章:いい人が報われないのは勿体ない ・・・いい人が報われない理由と、戦略的いい人とは何かを解説
- 第2章:《戦略的いい人》で人生急上昇 ・・・戦略的いい人として成功するための具体的な方法
- 第3章:仲間と楽しむチームワーク ・・・チームワークを通じて成功するための方法
- 第4章:楽しさも売上も膨らむ組織づくり ・・・組織でのリーダーシップと、チームを活かす方法
- 第5章:《戦略的いい人》のお金の使い方 ・・・戦略的いい人としてのお金の使い方
第1章で本書のキモである「戦略的いい人」について学びます。第2章から具体的なマインドセット、行動について学びます。第3章では人間関係にフォーカスを充てています。第4章・5章は、立場が上というか人をまとめたり部下などの責任を持つような目線の考え方になります。
第5章は、組織の中にいるサラリーマンはあまり馴染まない内容が多めかもしれません。
印象に残ったこと①戦略的な「いい人」の考え方
本書では戦略的いい人を、以下のように定義しています
- 「誰とも戦わずに、人の力を借りまくって成功する生き方・働き方をする人」
- 「自分だけでなく、最終的にみんながトクする考え方をする人」
特に1つ目の「人の力を借りまくる」と聞くと、なんだか甘いような良い印象を受けないかもしれません。でも本書では「得意な事は自分でやって周囲にギブする、苦手な事を人の力を借りる」としています。つまり全てを周囲にお願いするスタンス、というわけではありません。
苦手な事を周囲に相談して対応してもらうには、当然自分がこれまで何かをギブしてきてこそ、です。自分が得意だと思っていることをやるのは、苦手な事をやるよりもずっと楽しいですし生き生きと取り組めるのではないでしょうか。それをやって更に人に喜んでもらえるのなら、これ以上の喜びはありません。
また、本書では「頑張ることと成功は無関係」と言い切っています。頑張ることは素敵な事です。でも頑張ったからと言って100%成功するとも言い切れません。ならば、頑張るかどうかは一旦置いておいて成功しやすい働き方ってなんだろう?てときに「戦略的いい人」というノウハウを本書は提案しています。
ここで、夢中という言葉出てきます。戦略的いい人は「がんばるのではなく、まずは自分が夢中になる」ことを理解している。そして誰かを幸せにすることが出来るひとである、と。それには戦略が必要。戦略はすなわち、思いやりである。相手の目的を先に果たしてあげて、人に頼り自分の目的を達成する。だから自分が得意な事であればギブする、それも先回りして。
では、頑張らずに人に頼るには?本書では「ブリッジの視点」を提案しています。何かと何かを繋げる橋渡しをする役目を持つこと。これによって自然と人に頼ることが出来るようになります。ブリッジの視点とは下記のような何かと何かを繋げます。モノでも良いですし抽象的なものでも対象となります。
- 人と人をつなぐ
- 人とモノをつなぐ
- 人や組織の価値を言語化する
- 上司(主宰者)や部下(参加者)が発言しにくいことを代弁して橋渡しをする ・・・など
人と人は、まさに人脈と言えます。チーム内にはないが、いま必要としているスキルや知見があった時、〇〇部署の▲▲さんなら知っているかも、といったものです。モノは何かを実現したいときにこの製品・サービスで出来ますよ、と提案する。
一方で言語化。これは言語化のみならず可視化がすべて当てはまると思います。議論をしているがずっと口頭で話しておりいわゆる空中戦な時に、メモ帳で文章を起こしてみたり、パワーポイントで絵を描いてみたりして、空中戦な議論から地に足のついた議論へとつなげる。
代弁、これは特に新入社員や新しく部署に入った人ならすでにいる人達から「我々はここの部署が長く価値観が固まっているから、新しい目線で物事をみて意見を言ってほしい」と言われる事、ありませんか?これが一番イメージしやすいシーンかと思います。ならばフレッシュじゃないなら使えないやり方か、というとそういうわけではありません。
例えば、「自分の認識に違いがあったらいけないので、確認したいのですが・・・ということでしょうか?」といった確認を行うことで、依頼する側・される側の橋渡しになります。この部分は特に聴覚障害を持つ人は良い切り札があります。「聞き取れたか自信が無いので、確認したいのですが・・・」という枕詞を使う事です。
私は結構これはやります。何か会議をしていて、シーンとしてしまったとき。ここで「ごめん、ちょっとうまく聞こえていたか自信ないので」と自分に非があるようにして、再確認や話の再開につなげるような事をやっています。これは聴覚障害を持っていることを周囲が知っているからこそ成立するテクニックかなと思います。もちろん、健聴者でも使えるやり方でもあると思います。特に今だとオンライン会議が多いのでイヤホン・家のネットの調子が悪くて聞き取れなかったとか、ヘリが通って一瞬わからなかったとか・・・・。とはいえ、あまり多用するとちゃんと聞いている?と思われそうなので、うまく使うのがいいかもしれません。
印象に残ったこと②戦略的いい人の具体的な行動・マインドセット
戦略的いい人になるメソッドのイージーモード3原則を提案しています。
- 人に頼り、お願いする
- 人の手柄を周囲に伝える
- 巨人の肩に乗せてもらう
戦略的いい人になることは究極、その組織に貢献している人でもあります。全体的な利益を優先するため、何かコトがあったときにこれは対応すべきだ、と思ったらなんらかのアクションを取ります。それが自分がやると良いのなら自分がやってギブ、そのスキルがなかったりよりよいアウトプットを出してくれる人がいればその人に頼る。
人に頼るときも、指示ではなくお願いする形で行います。人に頼るのって案外難しいと思いませんか?なので「人に頼る」これも立派なスキルとも言えます。また、お願いする形なので「〇〇があるのだけど、どのようにやると良いと思う?いい方法あるかな?」と聞いてみる。
それもやみくもに聞くのではなくて、出来ればその分野が得意な人に頼む。なので、だれがどんな事に得意か、という事も理解しておくことも大切になります。人はやはり自分が得意な事を相談されたら、悪い気はしませんし、「やっとくよ」と言いやすいでしょう。
そして、2にあるように依頼した側は対応をしてくれたら、本人に感謝を伝えるのはもちろんのこと、その周囲にも手柄を伝えるようにすることが大事だと本書は述べます。2人だけの話にせず、「こちらは〇〇さんに対応頂いたんです」と全体に伝えるようにする。褒められるのは嬉しいことですし、この人の頼みを引き受けるとこんないいことがあると周囲に伝える事にもなりますし、〇〇さんはこういう事が得意なんだ、と他の人も知ることが出来ます。
最後に3の巨人の肩にのるですが、会社であれば、社内のキーパーソンは誰なのかを理解しておく。人事は誰かの采配で決まる。なので、そのカギを握る人を知っておくこと。頑張れは出世できる、ではない。この「巨人の肩に乗る」はいかに成功に近づけるかの近道です。巨人の肩に乗る方法として、本書は以下をあげています。
- 組織に貢献する
- 懐に入る
- 頼まれ事に答える
- 信頼されて重要な事をまかされる
- 周囲から納得を得る
こちらでも、「組織に貢献する」がキーワードとなっています。結局のところ、目上の人や会社は、「全体の最適のために動いてくれる人」を求めてます。だからこそ、何かを達成するために得意な分野を得意な人がやる、これが一番すぐ出来ることですし、精度も良いのでコストも低く会社としては理想な姿なわけです。もちろん場合によっては教育として、その分野に明るくない人が時間をかけてやることもあるでしょう。
組織に貢献する、という事はチーム全体にも貢献する人である、それが戦略的いい人なのです。
印象に残ったこと③戦略的いい人であるためのお金の使い方
第5章では、お金をテーマにした話になっています。こちらで印象に残ったのは、疲れの予防にお金を使う考え方。これはイライラ予防にもつながります。イライラは疲れからきているので、疲れ予防にお金を使う、ということです。これも戦略的いい人を保つ秘訣なのだそう。
確かに、疲れていると余裕がなくなってしまい、人に頼むのもついつい上から目線になってしまったり、自分でやる!と変に抱えてしまう事があるかもしれません。このように疲れを解消する方法に、お金で解決出来る事があるのならそれに使うのも、良いお金の使い方かもしれません。無料で出来るものがあれば、それにこしたことはありませんが・・・。
時間的な余裕を持つ方法として、家事とか外注出来るところは外注する考え方もあります。今は様々な便利な家電やサービスが出ているので、自分が苦手だと思っている家事は思いきって外注、すなわちお金を使うのも手でしょう。空いた時間でリラックスして疲れをいやしても良し、自己投資してキャリアアップなど図ってもよし、です。
まとめ
本書では、「戦略的いい人 残念ないい人の考え方」についてまとめました。ある意味スキル本ですが、どんな仕事をしている人でも使えるスキルだと感じました。「戦略的いい人」になることで組織に貢献し周囲を幸せに、自分も幸せにすることが出来るのであれば、一度試してみる価値はあるのではないでしょうか。

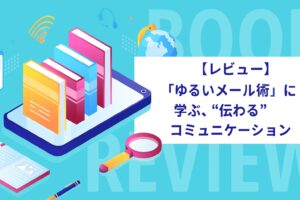
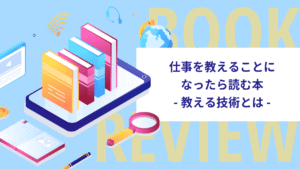

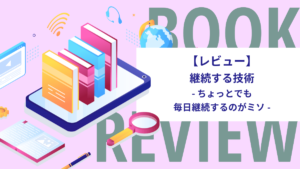
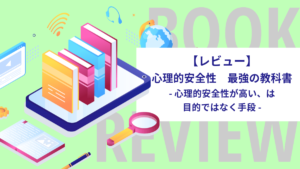
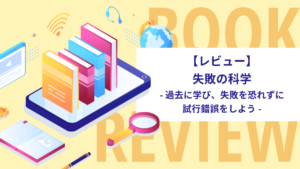
コメント