新年度になり、同僚や後輩に仕事を教える立場になった方に向けて、『教えるスキル』をわかりやすく学べる一冊を紹介したいと思います。「管理職」の立場に関する本は多くあれど、いわゆる先輩的な立場で、またはその業務では経験が長く同僚や教える必要が生じた立場の人向けです。管理職向けの本は数多くあれど、先輩向けは案外少ないので、きっと参考になると思います。
本のかんたんな紹介
2021年4月に発売され、作者は濱田 秀彦氏。株式会社ヒューマンテック代表取締役を務めており、マネジメント、コミュニケーション、キャリア開発のコンサルタントとして毎年150日以上の講演・セミナーを行っています。本書以外に上司・部下それぞれの立場の悩みや働き方に関するヒントを得られる書籍を多く出版されています。
対象読者
職場で同僚や後輩に仕事を教える立場になった先輩格の方々を主な対象としています。「これまで指導経験がない」「教えることに自信がない」といった不安を抱えている方に向けて、教えるスキルを体系的に学び、実践できるようになることを目的としています。特に、教える立場が初めてのビジネスパーソンにとって、心強いガイドブックとなるでしょう。、また、「教えるスキル」は職種問わずどこでも活躍できるスキルとして紹介されています。
本書を読んでみて
本書は大きく5章構成で展開されています。
第1章「知識の教え方ティーチング」では、仕事の手順やルールといった知識の伝え方を具体的に解説しています。
第2章「技術の教え方トレーニング」では、仕事を実際にやってみせ、できるように指導する方法について述べられています。
第3章「意識の高め方コーチング」では、主体的に仕事に取り組む意識づけの方法を紹介。
第4章「教えるためのサブシステム」では、教え方を標準化してチーム全体で共有する重要性を解説しています。
第5章「教えるタイプ教わるタイプの相性」では、教わる側の個性やスタイルに応じた柔軟な指導方法がまとめられています。
教える上で、「知識」「技術」「意識」は3点セットです。
印象に残ったこと①知識の教え方ティーチング
知識を教える段階では、「知っている」という状態を作ることがゴールです。手順は以下とされています。
①動機付け(モチベーションを上げるために行う)
②説明(ティーチングの中心)
③効果測定(知識の理解度や定着度を確かめるのテスト)
①動機付けは2つのパターンを使う
1. メリット獲得アプローチ →今から説明することを知っていると何が嬉しいか・良いか的な事
2. デメリット回避アプローチ →今から説明することを知っておかないと、今後苦労するよ、的なこと
②説明は以下のステップで進める
ステップ1:話材を準備する
ステップ2:組み立てる
③効果測定 インプットした知識をアウトプットさせる方法が最も有効。問題を出す。口頭試問でOK。
印象に残ったこと②技術の教え方トレーニング
ティーチングのゴールが「知っている」ことに対し、トレーニングのゴールは「できる」こと。そのため、効果測定をより細分化して行うことがトレーニングのポイント。
①動機付け
②やってみせ
③説いて聞かせて
④させてみて
⑤ほめて
⑥見届ける
※覚えやすいように山本五十六の言葉を寄せている
②やってみせ、の時はあくまでデモンストレーションのみで解説はしない。解説(その操作の理由など)は③説いて聞かせて、のタイミングにすることがポイントです。まず具体的な操作や手順を黙ってみてもらって、一通り終わったら、この操作の理由はね・・・と説明する。人は理由があると、「そのためなんだ!」と理解も深まります。
そしたら実際にやってみてもらって、フィードバック。出来ない事が多いでしょうから、良かった点1つ、改善点2点という配分でフィードバックすると良いそうです。
印象に残ったこと③意識の高め方コーチング
最後にコーチング。ティーチングとトレーニングは先輩側が持っている知識を継承するものでした。一方、コーチングは相手の中から引き出していくもの。そのための方法が「コーチング」。2つのスキルから成り立ちます。「傾聴」と「質問」です。
傾聴のポイントは、①目を見て聞く、②相槌を打つ。①は会社で上司や先輩に質問があって席まで行ったときに、PCから目を離さずに対応されたこと、ありませんか?あれって正直やられている方は良い気分はしませんよね。でも、自分の行動を振り返ってみると、案外自分がやっていることもあるものです。声をかけられたら、目の前の作業は一旦おいて声がした方向に体ごと向けるようにしましょう。
次に質問。こちらは質問には「オープン質問」を使うのがポイントです(オープン質問・・・はい/いいえではなく、自由に答えられること)。例えば、「今、何か問題ある?」だとクローズ質問で、つい「いいえ」と答えてしまいがちです。そのため、「いま、問題だと思う事は何?」だと考えさせることで、問題だと思う事に気づかせる。
ただ、人によっては自分の中で考えて答えを出すのに慣れていない人もいるもの。なので沈黙が起こってしまうかもしれません。沈黙が起こっても30秒は待つようにと本書は説明します。それでも出ない場合は、宿題として考えてもらうのも手でしょう。または質問のハードルが高いようだったら言い方を変えて、相手の考えのサポートになるような言葉をかけてみるのも良いでしょう。
まとめ
本ブログでは触れませんでしたが、5章ではこれまでの章はセオリーだったが、教える側/教わる側、それぞれのタイプごとに、感覚に応じてチューニングする方法を解説。本書内に簡単なアンケートがあるので、教える側/教わる側それぞれを4パターンに分類していきます。
1. 直観と行動の人
2. 成果と効率の人
3. 協調の人
4. 考える人
各パターンに教え方/教わり方のタイプがあります。なので、知識・技術・意識を十分意識しているけど、どうもなんか手ごたえがないな・・・とか、もっと意識した方がいいことがあるだろうか?というステップアップ的な内容として学ぶことが出来ます。
以上、本書は単なるマニュアル本ではなく、「知識」「技術」「意識」という3つの観点から仕事を教える方法を丁寧に解説した実践書である「仕事を教えることになったら読む本」の紹介でした。同僚や後輩に仕事を教える立場になった方にとって、本書は非常に心強い指針となるでしょう。教えることに不安を感じている方や、よりよい指導方法を模索している方は、ぜひ一度手に取ってみることをおすすめします。
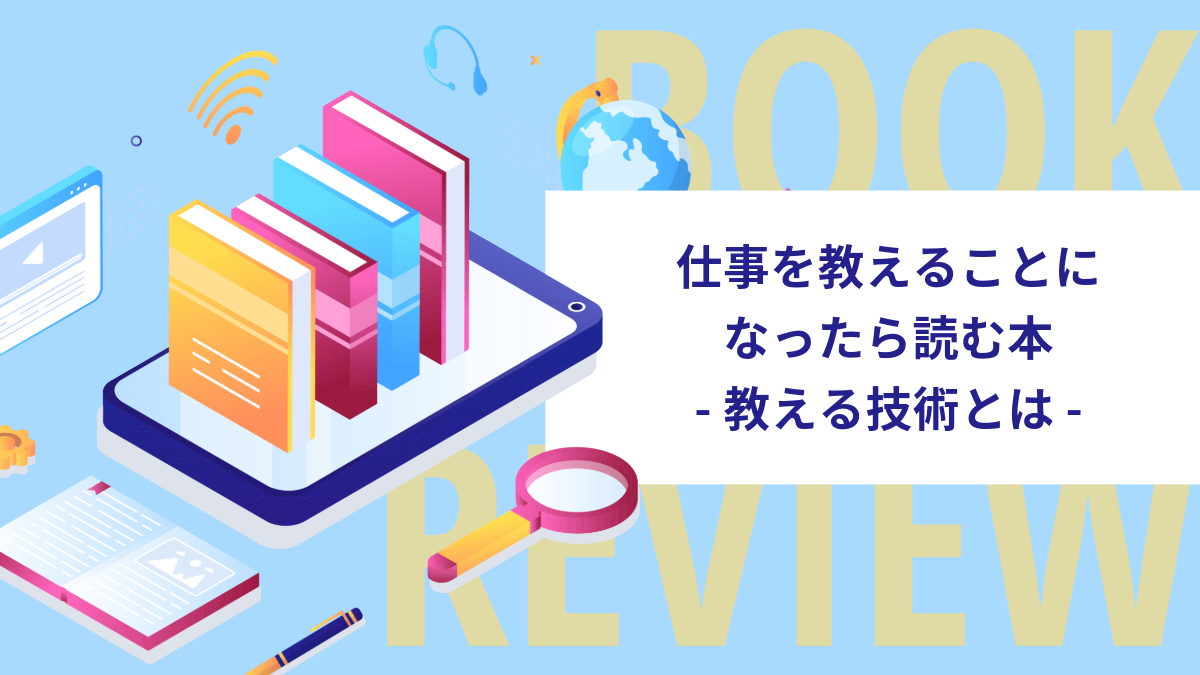
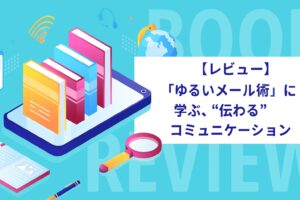


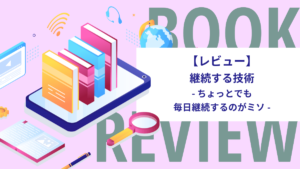
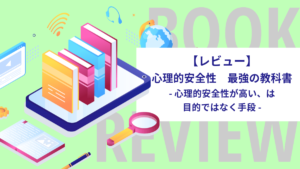
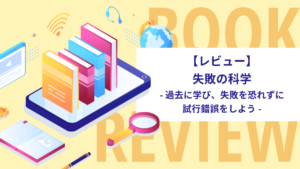
コメント