メールを書くのが苦手。
ビジネスメールになると、もっと悩んでしまう——。
そんな悩みを抱えている人にこそ読んでほしいのが『ゆるいメール術』です。
本書は、「正しく書こう」ではなく、「伝わればいいじゃないか」というメッセージをベースに、現代のメールコミュニケーションに向き合う一冊。タイトル通り、本文も緩くビジネス書というよりは読み物として気軽に読めます。
特に、聴覚障がい者の方や電話が苦手な人など、「テキストでやりとりする機会が多い人」に推奨します。なぜなら電話対応などを他の方にお願いするケースが多いため、その代わりといっては変ですが「メール対応は任せて!」とメールを自分の武器にしてしまうのです。その武器化に、この本はきっと役に立ちますよ。
■ 本のかんたんな紹介
▼ 対象読者
- メールの書き方にいつも時間がかかってしまう人
- 堅苦しい表現ばかりで、自分の言いたいことが伝えられないと感じている人
- 聴覚障がいを持ち、電話以外の伝達手段としてメールを使っている人
▼ 本書で得られること
- 相手を不快にさせずに、伝えたいことを届けるメール術
- 完璧じゃなくていい、でもあたたかい言葉の選び方
- 感謝をベースにしたやりとりで関係性を築くコツ
■ 本書を読んでみて感じたこと
#1 「伝わるか・不快感がないか」がメールのキモ
そもそもなぜメールを書くのでしょうか?メールは正しい文章を書くことが目的ではありません。相手に何かを伝達しアクションをとってもらう、それがメールの目的なはずです。だから完璧な文章よりも、「ちゃんと読めて、意味が伝わる」ことの方がずっと大切なのです。
多くの人が「正しい表現」にこだわりすぎて、逆に「伝わりづらい」メールになっていることがあります。
でも本書は、その逆を教えてくれます。
まず大事なのは「伝わるか」「不快感がないか」。この2つだけで、メールの印象は大きく変わります。
たとえば、文章がぎっしり詰まっていたり難しい言葉が多用されていたら、それだけで読む気が失せてしまうもの。
読んでもらうには、1行あたり20~30文字で改行を入れる、中学生でも理解できる言葉・文章にするといったテクニックが紹介されています。
一方で、わかりやすさを重視したあまり箇条書きだけのメールもどうでしょうか?わかりやすいかもしれないけど、そっけなくて相手は自分を軽んじている、と思われてしまうかもしれません。つまり不快感を与えてしまっています。これが直接ではないにせよ取引停止の一因になってしまう可能性もはらんでいます。
さらに、メールは“記録として残る”からこそ、感情的な言葉は避けるべきという指摘も。
その場の怒りや焦りを反映させた文章は、後から見ても自分に返ってくる可能性があります。だからこそ、落ち着いて、目的を達成する文章を意識する。それだけでトラブルを未然に防ぐこともできるのです。
#2 メールであまり悩まない!
ビジネスメールは、悩みの温床です。
「この表現で失礼じゃないかな」「この語尾、強すぎないかな」…と、書いては消しての繰り返し。でも、メール作成をしていく上で守ってほしいのは「伝わるか」「不快感が無いか」です。
そうは言ってもじゃあ具体的にどうすればいいのか、以下のような考え方が紹介されています。
- 敬語はまずは丁寧語を抑え、丁寧語ベースに書いていこう
- 誤字や脱字ミスを防ぐことに躍起にならない(致命的な誤字でなければ、人は気にしない。スルーする
- 曖昧な表現を避けよう
敬語は尊敬語・謙譲語・丁寧語があります。もちろんこれらを使いこなせることが一番ですが、まずは丁寧語さえ押さえておけば大やけどはしません。余力があれば尊敬語・謙譲語も少しずつ取り入れていくといいかもしれません。
誤字・脱字ミスは致命的でなければ血眼になって自分の書いたメールを読み返す必要はないでしょう。もちろんないことにこたことはありませんが・・・。
では、致命的な誤字は何でしょうか?例えば値段や数量、人の名前や地点など、何等かの損失を被ってしまうようなキーワードは気を付けるべきです。これだけは血眼になってチェックしましょう。なぜなら、後々のトラブルに発展しがちな箇所だからです。
最後に、曖昧な表現。例えば「なるべく早く」といった文章を書くことありませんか?でもこれはメール受け取った側は「本日中かな?」と考えたものの自分は明日中だと思っていた、となると受け取った側は遅れているじゃん、とネガティブイメージを持ってしまいます。だからこそある程度明示しておくべきですー18時”頃”とか。
18時頃、これもやや曖昧な表現です。でもそれでいいのです。なるべく早く、よりはぐっとわかりやすい。で、こうやって期限を決めておくと、自分へのケツもたたくことが出来ます(笑)曖昧な表現にしておくと「いつやろう・・」と迷ってしまいませんか?だからこそやや曖昧な表現で良いので明示する、これは相手にとっても自分にとっても利点となります。
#3 謝罪フレーズを多用しない
日本人は特に「すみません」「申し訳ありません」を多用しがちです。
でも、それが逆に自分を追い込んでしまうこともあります。本書では、お詫びフレーズを多用すると、パワーバランスが崩れてしまうと指摘されています。また、本当に謝らないといけない時、切り札的な使い方が出来ず損をしてしまいます。
小さなミス、例えば添付ファイルをつけ忘れた時なら「失礼しました」。
中くらいのミスであれば「申し訳ありません」、大きなミスであれは「大変申し訳ございません」といった風にミスの度合いで使い分けをする。
逆に謝罪フレーズを使わなくていいシーンでは御礼フレーズを使うことも、本書は提案しています。「お手数をおかけして申し訳ありません」よりも、「ご対応ありがとうございます」のほうが、受け取る側の気持ちはずっと明るくなります。
「ありがとうございます」を基本にすると、自分も相手も気持ちよくなれます。
もちろん、ミスや迷惑をかけてしまったときには謝罪が必要ですが、そうでない場面では「感謝」を伝えるほうが建設的です。
言葉って不思議で、「ごめんなさい」より「ありがとう」の方が、関係が続きやすくなるんですよね。
この“言い換え”の考え方は、ビジネスだけでなく、日常のコミュニケーションにも活かせると感じました。
■ まとめ
『ゆるいメール術』は、「伝える」ことの本質を教えてくれる本です。
堅苦しいマナーや完璧な文章ではなく、“思いやり”や“温度感”を持ったやり取りこそが、信頼関係のあるメールになるということ。
・正しく書こうとしすぎないこと
・読んだ相手の気持ちを想像すること
・謝るよりも感謝を伝えること
この3つのポイントを持っていれば、誰でも心のこもったメールが書けるはずです。
メールに時間をかけすぎていた自分にとって、本書は“肩の力を抜くきっかけ”を与えてくれました。
メールで悩んでいるすべての人に、自信を持っておすすめしたい一冊です。
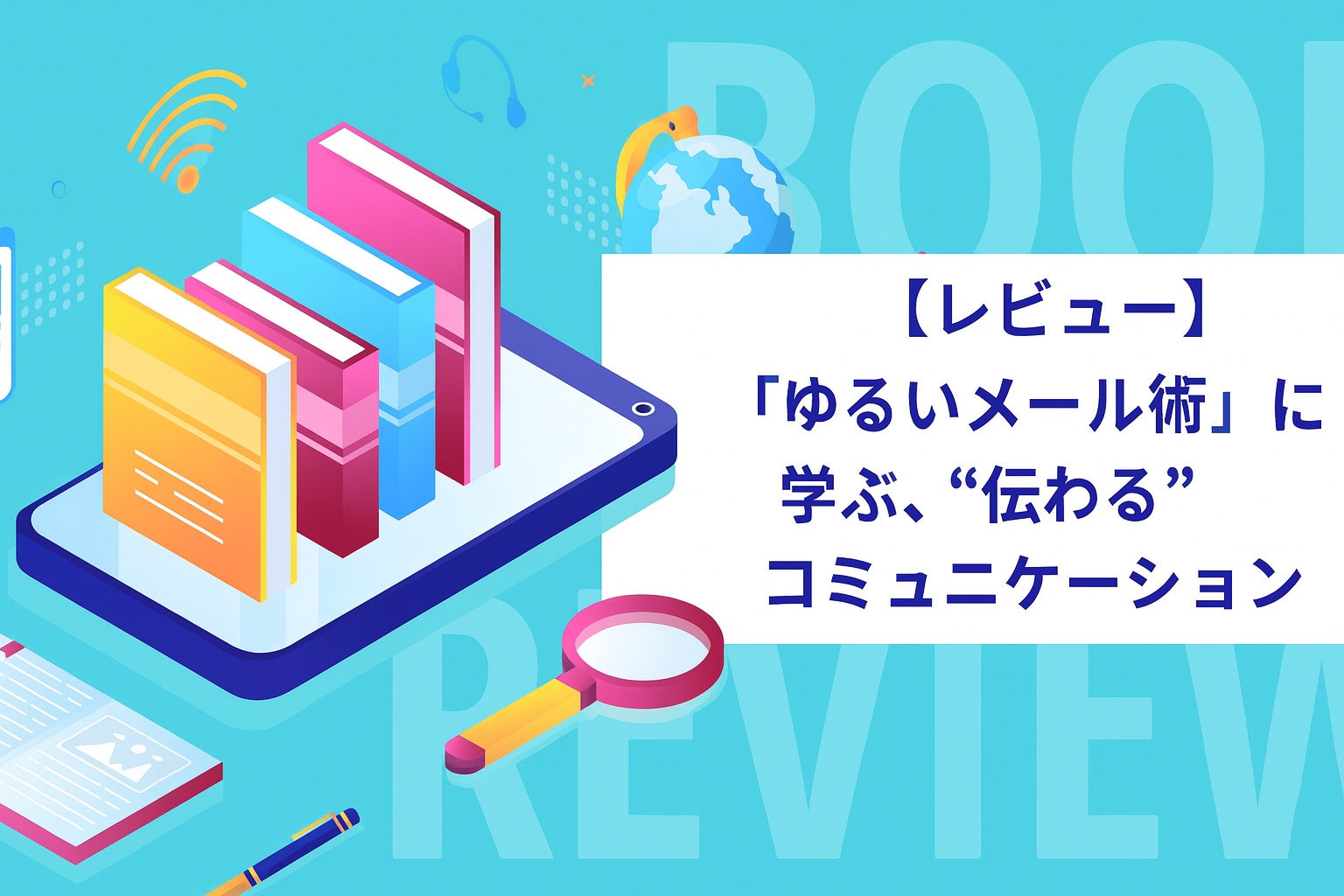

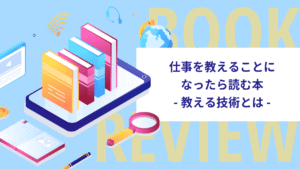

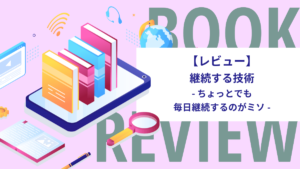
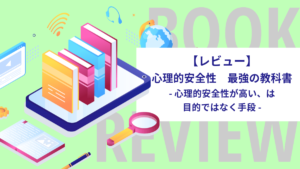
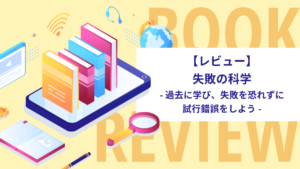
コメント