職場で自分に直接、罵倒してきたり、悪い態度をしてきたりしているわけではないのに、なんだか自分が責められているような気持になってしまうことありませんか?また自分のちょっとした言動で、雰囲気が怪しくなったりその後ぎくしゃくしてしまう事もありませんか。
それはもしかしたら「無礼な態度」のせいかもしれません。無礼ってきくと、ドラマとかで地位の高い人が「無礼者!」という言葉でなかなか普段自分たちの言葉で出てこない言葉ですが、本書ではこの無礼と礼儀正しさについて述べています。
本のかんたんな紹介
2019年6月に発売された書籍で、クリスティーン・ポラス(著) 夏目 大(翻訳)となっています。著者であるクリスティーン・ポラス氏はTEDでも、本書にまつわる公演を行っていますので、TEDからも知っている方も多いのではないでしょうか?また「漫画で分かる」シリーズでも本書は出ています。
対象読者
主にビジネスの場を対象としているのでビジネスパーソン向けですが、最終的には「人づきあい」にフォーカスを充てているので学生でも、リタイヤ済の人でも人づきあいに考えるよいきっかけになると思います。そのため、また管理職やそうでない人、どちらにも読んでおきたい1冊です。
本書で得られること
「無礼」とは何なのか、そしてビジネスの場でそれがいかに悪影響を及ぼすのかが分かります。そこで、無礼な人にはならないように自分がどう気を付けるか。また無礼な人では無いだけでなく、周囲を励ます事が出来るような「礼儀正しい人」になるには?
そして、周囲に無礼な人がいた時の対処法も学ぶことが出来ます。
本書を選定した理由
社会人10年を迎え、少しずつ仕事に慣れ周囲を見る余裕が出てきました。仕事に慣れておらず余裕がないと、目の前の仕事をこなす!という事しか持てませんでした。しかし、少し慣れて目の前のタスク以外に目を向けてみると、目の前のタスクが出来ることだけが仕事の全てではないと感じるようになりました。
昔はコミュニケーションスキルとかなに?目の前のタスクをこなすことだけが必要でしょ?ってなっていたのですが、いかに周囲の人とうまくまわしていくか、も大事なのだと気づくようになりました。よく敵を作らないようにするとか聞くけど、具体的にそれってなんだろう?と思い、本書を選定しました。
本書を読んでみて
1章~14章の構成となっています。1~4章では、無礼とは何か、無礼による社会的なデメリットを学びます。そして礼節のある人はどんな人でどういうメリットがあるかを学びます。
5~9章は、自分が礼節のある人になるにはどうすればよいか具体的な方法について説いています。10~12章では自分以外に礼節のある人を採用したりいかしたりする方法について述べています。
そして最後、13~14章で身近に無礼な人がいるとき、どうすればよいか?を学ぶことが出来ます
印象に残ったこと①礼儀正しさとは、なぜ無礼はいけないのか
そもそも無礼はなぜいけないのでしょうか?人を傷つけてしまうから良くないとかはなんとなく感じる事でしょう。本書は無礼な人がいることで経済的なデメリットがあると説いています。
無礼な人は周囲の人間だけでなく、会社にも大きな影響をもたらすのだ。
無礼な人がいると、周囲の人々の健康を害してしまいます。その結果、病気による休職や早期退職が起こりえます。
また生産性の低下も見逃せません。無礼な人がいると、周囲の集中力を下げてしまいます。仕事に取り組んでいたら、周囲で上司が部下を叱責している様子が見えてきて、まるで人格否定するような態度や言動を見ると、まるで自分に言われているような感覚になって、なんだか居心地が悪いような感覚を覚えたことはありませんか?
そういったネガティブな気持ちは、無駄に体を緊張させ仕事への集中力が低下してしまったり、新しいアイデアを出すといったクリエイティブな活動が縮小されてしまうかもしれません。本来の自分の力を発揮できなくなってしまいます。これだと、会社そのものにも「ソン」ですよね。
もし無礼な人が1人だけなら、その人に集中的に無礼な行為をやめるよう指導するとか、極端に言えば人と接しない業務を与える事も考えられるでしょう。しかし、
無礼さというのはウイルスのようなもので、人から人へと感染していく
つまり、身近に無礼な人がいると周囲もそれにつられてしまうというのです。だからこそ、1人1人が今の行動は無礼ではなかったか?相手のパフォーマンスを下げてしまうような言動ではなかったか?と意識することが大事です。
チームの仕事ぶりを悪く言われると、皆、他のメンバーを信用しなくなり、無意識のうちに心を閉ざしてしまう。他のメンバーに意見を求める事は減り、たとえ意見を言われても受け入れなくなる。
また、何か新しいことを思いついても試してみようとはしなくなる。ミスをしてもそのことを誰にも話さない。問題が起きる問題に気づいても、それを他の人に連絡しない。自分たちのことを悪く言う人間がたとえそばにいなくても、一度、侮辱的なことを言われると、その陰が消えなくなり、チームのメンバーは最善を尽くそうとはしなくなる。
どうでしょうか。無礼な人がいる事によってとても働きたいと思えるような環境じゃなくなってしまいますよね。仕事自体は移り変わりの激しい社会では大変な事なのに、更に人間環境も悪いだなんて苦痛です。それにサラリーマンでは1日8時間は仕事します。人生の中でも大きな時間を占めます。だからこそ、良い環境で働きたいですよね。
だからこそ自分が礼節のある人になるにはどうしたらよいか、無礼ウイルスを断ち切り礼節ウイルス(?)を広げられるか。また、無礼な人に遭遇した時、どのようにして自分を守っていくのか、について説明していきます。
印象に残ったこと②自分が礼節のある人になるには
まずは自分自身が礼節のある人になることについて考えます。そもそも礼節のある人、とはどんな人でしょうか。無礼でなければ良いのか?本書は礼節のある人を以下のように説明しています。
実際に無礼でないだけでは、ただ中立的なふるまいをしているにすぎない。ただ誰も傷つけていないというだけだ。礼節ある人とみなされるためにはそれ以上のことが必要だ。他人を尊重し、また品位を感じさせる丁寧で親切な態度で、周囲の人達の気分を良くしなくてはいけない。
無礼でなければOK、ではないのです。さらには「話してみていい感じだな」「なんか元気出た」と相手の気持ちを和ませるような言動をとれる人の事を礼節ある人と本書は解いています。
なんだかハードルが高そうな礼節ある人。そんな人になることに具体的なメリットは、何でしょうか?本書では礼節のある人になることで以下の3つのメリットがあるとしています。
1. 仕事が得やすい
2. 幅広い人脈が築ける
3. 出世の可能性が高まる
1. の仕事が得やすいは言い換えると何かあった時に声をかけやすい人物である、という事です。何か重要な仕事が発生した時に、声がかかるかどうか。すなわち、2と3にもつながります。人望がある、とも言えるのではないでしょうか。
とはいえ、無礼な人でも上り詰めてしまった人もいる事からも、礼節のある人であれば必ずクリエイティブな仕事が出来て周囲に恵まれ出世することが出来るか、というとそうは言い切れないと思います。でも、どうせなら無礼な人だなとネガティブなイメージを持たれるよりも礼節のある人だなと思ってもらうほうが、良いのではないでしょうか。
また、「声がかかりやすい」というと小さな仕事、誰でも出来そうな仕事もぽいぽい依頼されてしまうのでは、と思ってしまいそうです。そういう仕事だからこそ丁寧に取り組み、相手に恩を売るという考え方もあるのではないでしょうか。もちろん他に優先しないといけないタスクがあればその理由を述べて断るのも大事な事でしょう。
自分が礼節を保つ事が出来ているかを確認するには以下の7つの方法が挙げられています。
①他人からフィードバックをもらう
②できるコーチの指導を受ける
③同僚や友人に協力してもらいチームで改善に取り組む
④ゴールドスミス式360度フィードバックを利用する
⑤人の感情を読み取る訓練する
⑥毎日、日記をつけてみる
⑦「食う・眠る・動く」で自分を大切にする
①~④は他人に依頼するので難しい所があるでしょう。一方⑤~⑦は自分一人でもできる事なので、まずはそこから初めて、他人に依頼出来そうな所があれば頼んでいくと良いのではないでしょうか。⑤は人の観察ですし。⑥は自分の観察です。⑤は小説を読むのも効果的かもしれません。本書ではないですが、小説は人の感情を文章で説明しているので、こういう感情があるのかと訓練になるようです。
⑦は言わずもがな。そもそも自分の精神にゆとりがなければ礼節のある人、という状態にするのは難しいでしょう。自分を大事に出来て他人にも大事にできるのではないでしょうか。
本書では礼節ある人が守る3つの原則があるとしています。
①礼節ある人は笑顔を絶やさない
②礼節ある人は相手を尊重する
③礼節ある人は人の話に耳を傾ける
様々なビジネスライフハックの本で見聞きしたありがちなキーワードが並んだかもしれません。でも、あちこちで見られるという事は、共通した良い行動であり、かつ、なかなか実現が難しいことである、と言えるのではないでしょうか。
ちょっとしたことでムッとして笑顔でなくなってしまう事や、「この人は話が長いんだよねー」と下に見てしまったり、話しが長いので遮ってしまったり・・・、と正反対の行動をとってしまい、後で何で自分はこうなんだと責める事もあるでしょう。
3原則を意識しふるまう事で暖かい人だと思ってもらえ、有能な人だと思ってもらえる可能性が高まるとしています。自分自身もありたい姿を目指してみたら、周りからも好評となれば挑戦する価値があると思います。
印象に残ったこと③身近に無礼な人がいるとき
最後に、身近に無礼な人がいたときに自分を守る方法を学びましょう。
無礼な扱いを受けているときはどうすべきか。
助言はひと言にまとめると「あなた自身と、あなたの将来のことだけを考えるべき」となるだろう。
無礼な扱いをうけて様々な感情や思いを抱えてしまうかもしれません。それでも、
常に自分を保たなくてはいけない。決して自分を見失わないように気を付ける。ただ、無礼な相手の人間性や、職場の環境を、自分だけの力だけで変えられるとは思わないようにする。
と注意喚起しています。無礼な態度をされたとき、大人として相手と話し合うべきと思うかもしれません。しかし、本書では、条件が成立しない場合は相手と話し合うべきではないとしています。話し合うべきでないとなった時、相手との接触は4つの事に注意します。
まず会話を手短にする。相手にとって有用と思える事だけを話す。友好的な態度を保つ。そして、常に毅然とする。
仕事上、接触しないといけない場合もあるでしょう。やり返そうとかはせず、淡々とこなす事が大事です。
無礼な態度で心を揺さぶられようとも「自分は未来のために戦うべき」で、自分が成し遂げたい事や目的を持つ事で無礼な態度に動揺しないマインドを持つことも、大切だと本書は説明しています。目標を定めて進歩していることを実感したり、メンターの助けを借りたり、規則正しい生活や、社外での活動をする・・・などで自分は未来の為に活動している、と実感することが大切です。
会社をやめよう、と思ってしまう事もあるかもしれません。会社を辞める前に、今の場所を離れた時のメリットデメリット、キャリアにどう影響するか、今の職場に居続けて仕事以外に悪影響があるか・・・などを考えた上で判断します。
まず他人にとらわれず、自分自身だけを見つめ、自分の成功だけを考えるようにする。何をすれば自分が成長し、発展できるかを見極め、それをすることに集中する。
自己中心的に感じるかもしれませんが、それくらい自分を中心において考えてみるのもいいのかもしれません。そもそも無礼を働いているのは向こうなのだから、自分を守る行動をして何が悪い?のマインドでいきたいものですね。
まとめ
礼節のある人とはなにか、ビジネス面でどのようなメリットがあるのかを述べ、自分が無礼な人になっていないか、礼節のある人になるにはについてまとめ、最後は無礼な人への対応法でした。まさに「礼節」をテーマに一貫した解説書ともいえる書籍です。
意外にも最後の無礼な人への態度はそっけない、シンプルに見えたのではないでしょうか。私は話し合うものだと思っていたのですが、「話し合う」べき相手かどうかかも考えるという視点はなかったので、条件に当てはまらない場合は話し合わない、というのは驚きました。
人と接するのはビジネスでもSNSでも、敵を作らないことに越したことはないでしょう。その方法の一つに自分が礼節のある人になること、でもあると感じました。だから、「最強の生存戦略」とあるのかもしれません。

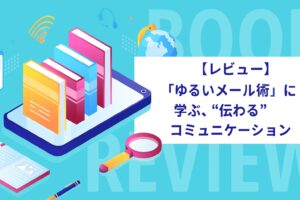

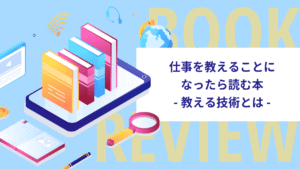
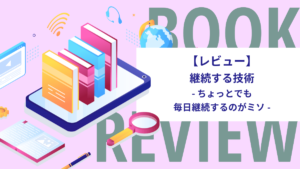
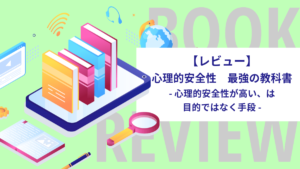
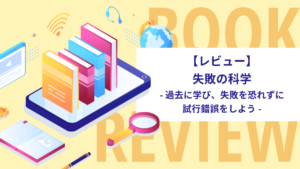
コメント